社会ソフト「日本」の研究 |
1997/12/01 歴史と社会 |
フランシス・フクヤマ氏は現代の資本主義社会について「合理的で利己的な人間(経済学者の描く人間像)で説明できるのは現状の80%までだ」と指摘する[i]。残りの20%は社会の慣習、道徳、習慣、つまり家庭制度や宗教心、国民性など私たちの「心」のなかの非合理的な部分である。多くの経済学者が熟知しているように、こういった非合理的な要素は国民経済に深く組み込まれて分離することはできない。グローバル化や情報化は、産業政策や経営システム、技術革新など近代的な産業構造を驚くべき勢いで移転させるが、慣習や道徳、習慣などの非合理的な社会ソフトは移転が難しい。
フクヤマ氏は「歴史」が終ったいま、世界は認知を求めて争われる「闘争の場」となり、その認知の舞台は、軍事力ではなく経済力に移行したと主張する。そして、産業システムの構築に関するノウハウや智恵がグローバル化や情報化によって行き渡った後で、経済パフォーマンスを真に決定づけるのが、最後まで残る社会ソフトの差であるとする。いまや、文化はもっとも重要な社会ソフトの地位を経済学や経営学からも授けられつつある。
同様だがより過激な主張は、サミュエル・ハンチントン氏によって行われている。ポスト冷戦後、世界システムは平和と経済の時代から、再び暴力と軍事力の時代へと回帰し、その際の「チーム」分けは各地域の宗教を中心とする文明の親密度によって決まる、とする。ハンチントン氏の最新著書『文明の衝突』[ii]の最後に揚げられる未来シナリオは、「2015年過ぎにベトナムと中国間の衝突を契機に世界大戦が起こる」というものである。日本は中国やイスラムといわゆる「儒教—イスラム連合」を組み、アメリカ、ヨーロッパ、ロシア、ラテンなどの「クリスチャン連合」と対決するというシナリオである。
ポスト近代の闘争の場が経済に限定されるとするか、軍事力の世界まで再拡大するとみるのか、あるいは、日本を信頼に足る社会と置くか、西洋的価値観と結局は折り合えない国として描くか、といった違いはある。しかし、ポスト近代化の時代を迎える21世紀の世界システムで各国がどのような位置を占めるかは、宗教や統治の歴史がつくり出した、その地域地域での慣習、道徳、習慣であるとする点で、フクヤマ氏とハンチントン氏の論は一致している。
ポスト冷戦後、アジア出身の唯一のサミット参加国にして、GNP世界第2位の大国日本。経済力が認知の指標となればなるほど、そしてある程度の経済パフォーマンスを示す限りにおいて「日本という社会ソフト」は、世界から賞賛とともに非難や嫉妬、そして警戒心を集める存在であり続けるだろう。他の先進国からみれば、集団主義や間人社会、イエ社会、タテ社会といった言葉で表現されてきた「日本という社会ソフト」の研究なしに、説得力のある国際的な比較社会学は成立しないのが現状だ。一方、日本人にとっても、日本という社会ソフトのどこに経済力を生み出す優位性があり、それは未来も続くのか・・・という不安にも似た疑問が頭をもたげ始めている。
本稿では、これまで「日本という社会ソフト」を世界の識者がどう認識してきたのかを整理しながら、その変質の状況を捉え、日本社会の近未来を描いてみたい。
Ⅰ.イデオロギー化されやすい社会ソフトの国際比較
論議を進める前に、比較社会学という学問分野が世のイデオロギーと密接に結びつきやすいことを指摘しておく必要があろう。そうした傾向の故に、セオリー自体を「メタ」な視点、すなわちそのセオリーが生み出されたり、受け入れられる時代背景と照合しながら冷静に見比べる作業が求められる。
すべての文化には、「個人の自立性」と「集団への帰属性」の双方がある、その配分と強弱、結合の仕方は国によって大きく異なっている。社会ソフトは、個人の自立と集団への帰属を結びつける、それぞれの社会独特の慣習や道徳、習慣などの仕組みである。かつて日本社会の特徴として指摘されてきたのは、一貫してその片方向側—集団主義であった。
しかし、その評価は、日本経済が脚光を浴びるに連れ大きく変わってきた。
筆者の観察では、次のような理由によって各国の社会ソフトに対する比較研究は、その時代の社会状況や価値観と深く結びつきやすい。
●「社会ソフト」比較論は国家のパフォーマンスに対応して変わる
「国家の社会ソフト」理論は、軍事力や経済力など目に見えるメルクマールを説明できなければ説得力を持たない。したがって、国力の順位が変われば理論や評価尺度も大きく変わることになる。たとえば、東南アジアの経済発展が無視できない現実となってきたら、その事実を説明し得ない理論は葬り去られ、説明可能な新理論が登場することになる。
●社会ソフトに関する研究は「イデオロギー」化しやすい
軍事力の圧倒優位がかつての「西欧至上主義」の根源にあった。それに代わって(フクヤマ氏が主張する)経済力を社会のメルクマールとする考えは、自国の社会体制のレジティマシー(正統性)を主張する上で、新しいイデオロギーとなり得る。とりわけ日本や4ドラゴンなど、西欧型個人主義へのコンプレックスに悩まされてきたアジアの経済発展国家においてそうした傾向は顕著だ。一方で、経済発展が停滞している西欧諸国では「まったく理念や宗教観の異なる国々で経済競争をしても仕様がない」という脱欧米型のイデオロギーに対する嫌悪感(一部のジャパノロジストの指摘やハンチントン氏の『文明の衝突』が好例である)が生まれる。「愛国心」と、それぞれの国の文化・道徳に根ざした「社会ソフトへの愛好」はほとんど同義である。
●社会ソフトの比較研究は官僚や政治家の注目を集めやすい
そもそも政治家は、産業政策の範疇に収まり切らない教育や道徳を含めた「国家の社会ソフトの更新向上」がその使命だ。一方、官僚はグローバル化のなかで、労働や家族制度など、国家間で移転が容易な産業制度だけでなく、より文化の領域に属する社会制度間においても、調整や擦り合わせを迫られる状況に直面している。その結果、「社会ソフト理論」は、政治家や官僚が自国の社会改革を推進したり、他国に対して自国制度のレジティマシーを主張する際の「武器」になりやすい。
Ⅱ.日本社会観の変遷
●敗戦ショックと単軸型集団社会観の時代
過去世界でもっとも有名になった日本社会観は、ルース・ベネディクト氏の『菊と刀』[iii]だろう。同著はアメリカにおける日本社会観のステレオタイプをつくり、また日本に逆輸入されて、戦後日本人の自画像をもつくり出すほどの影響力を持った。
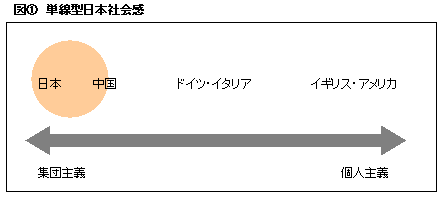
その社会観は、簡単にいえば、集団主義と個人主義を一線上の目盛りにし、アメリカ社会と日本社会を対極に、それ以外の国をその間に描くものである(図①)。
同じ構図は、「個人主義の前提を土台にしている度合いという点において・・・イギリス人やアメリカ人の対極にいるのが日本人である」[iv]とした、イギリスの碩学で知られる社会学者ロナルド・ドーア氏によっても唱えられている。
明治以降から昭和初期にいたる50年間、とりわけその最後の15年間、日本社会はその長い歴史においても特異な、天皇を頂点にいだくテオクラシー(神政)国家となった[v]。第2次世界対戦で国家社会主義を採用したドイツやイタリア、そして日本の集団主義的価値観に対して勝利を収めたのは、個人の自由に最高の価値を置くアングロサクソン型の価値観である。戦前のテオクラシー社会への嫌悪感と敗戦のショックは、こうした自虐的な日本集団社会観を、私たち自身が好んで採用する理由になった。江戸時代の自立経済組織としての「藩」の多様性や洒落な町人文化、あるいはもっと遡って戦国時代の「つはもの」(下克上社会における荒くれもの)どもの個人主義的価値観なども、日本人の血のどこかには残っている多様性を、日本人も世界も忘れてしまったのである。
第2次世界大戦後はソビエトや中国、東欧の社会主義国家が集団主義側に加わり、日本の居場所は民主主義の体裁を取り入れるに従って、やや個人主義側にシフトしてきた。しかし「日本株式会社」という言葉に表現されるように、「官僚制度の経済介入が日本の戦後の産業経済の繁栄をもたらした」とする見方が広まったことから、日本に対する集団社会観は依然強く残ることになった。この単軸型社会観は、企業や親睦団体、家族などの中間組織や、そうした組織と国家との関係がほとんど表現されず、専ら国家の社会組織への関与度をもって「個人主義」か「集団主義」かのメルクマールとするという意味で、近代的な社会観といえるだろう。
●日本の経済大国化とイエ社会型資本主義観
さて、日本社会を集団主義の一方の軸に置く社会観は、日本経済の飛躍的向上とともに陳腐化を来すことになった。非効率であるはずの「集団主義」のシステムの下、日本は個人主義に価値観を置く西欧諸国を凌ぐ経済パフォーマンスを示すに至り、しかもそれが持続することが明らかになったのがその大きな理由だ。集団主義を悪とし、個人主義を善とする価値観だけでは日本経済のパフォーマンスの説明が難しい。国家の統制が比較的強いと見なされてきた戦後の日本社会と、同じく国家統制が強い東南アジアの開発型国家との圧倒的な経済格差をも説明できなければいけない。そこで登場したのが「イエ型社会文明観」[vi]である。(図②)
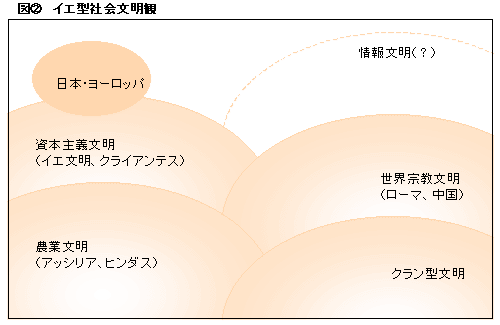
イエ社会型文明観は「枝分かれ文明観」とも呼ばれ、統合型文明と発展型文明が順番に人類が訪れるとする。新しい文明の軸を切り開くのは、その前の文明によって、影響を受ける周辺国である。インドや中国、ローマ等の有史宗教文明の枝分かれの後に登場したのはローマ文明の周辺にあったヨーロッパと、中国の周辺国にあった日本の農耕・戦闘を行うイエ社会。この2つの流れが今日の近代企業の原型となったとする文明観だ。
この文明観は、国家ではなく中間組織(イエや会社や親睦団体)に注目した点で近代的な—歴史を無視し、近代以降の国家体制によって社会を峻別する—社会観に痛撃を与えた。また中間団体の起源として近代以前からの社会制度の継続性—藩やイエ社会と企業との類似性—を主張したが、これは多くの日本人の実感と重なるものであった。日本経済の良好なパフォーマンスを、この100年余りの近代化と西欧の模倣のみによるものとするのではなく、日本人がもともと持っていた歴史的な社会ソフト能力によって説明することになり、経済発展によって自信を取り戻しつつあった日本人の「自尊心」をくすぐることになった。
中曽根・レーガン・サッチャーの新自由主義の時代に、日本が資本主義精神復興の旗頭となる上での精神的な支柱になったのが、同理論だったと結論づけることもできよう。
しかし、その後の世界情勢と同理論が乖離を始めたとすれば、韓国や台湾、シンガポールや中国の経済発展が、1980年代から90年代にかけてきわめてめざましい点にあるかもしれない—イエ型社会文明観では、有史文明国である中国や、その近隣国である韓国の経済成長をうまく説明することができないように思われる。
●日本の国際プレーヤー化と多元的資本主義観—1
次のセオリーは、ミシェル・アルベール氏が唱えた「ライン型資本主義(ドイツ・フランス)」と「アングロサクソン型資本主義(イギリス・アメリカ)」の対比である。アルベール氏は、早くから都市化を行い、また、証券金融制度に象徴されるように競争市場において大衆レベルまで経済リスクを分散させる「アングロサクソン型資本主義」と、広範な農民層を抱え、産業発展を金融資本や官僚、軍人、エリート資本家などが担う「ライン型資本主義」の対比があると説く[vii]。最終的には、より「セクシー」なアングロサクソン型資本主義がドイツやフランスのライン型資本主義を「飲み込む」と予想するものの、これまでひとつの方向をめざして進化していると思われた西欧の資本主義にも、歴史に起因する多元的な価値観が存在し、今後も差異が残り続ける可能性を示した。
この多元的な資本主義観の登場には、グローバル化のなかで西欧諸国(特にヨーロッパ)が、ECというかたちで汎ヨーロッパ経済に、そしてさらにアメリカを中核とする世界経済システムに飲み込まれつつあった事実が大きく関係していると思われる。
日本でこの多元的資本主義観が理解されやすいのは、明治以降の制度設計家—岩倉具視や伊藤博文、山形有朋ら—が、どちらの体制を輸入するべきか迷った末、どちらかと言えば同じく農業国家であり、エリートに国家運営を委ねるライン型資本主義制度を選択してきた歴史的体験の所以であろう。アングロサクソン型かライン型かの二分的な選択肢は、日本人にはお馴染みだったのである。この概念を図示すると、次のようになる。(図③)
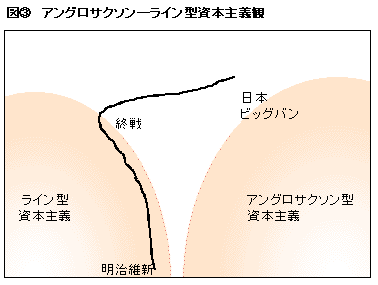
アメリカを基準にしたグローバル化(アメリカニズム)と、各国独自の多様な資本主義制度の擦り合わせを図る他国間主義(マルチラテラリズム)との軋轢が明らかになるにつれ、日本には(そしてヨーロッパには)、あるときにはアメリカを応援し、あるときはヨーロッパと(日本と)組むという政治的な多元主義への欲求が生まれている。アメリカの2国間において「規制か競争か」の資本主義的な価値観の刷り合わせをするのではなく、多元的な資本主義観のなかで対立関係を相対化したいという欲求[viii]が、日欧の双方で多元的資本主義観が流行る背景にあるように思われる。
その後、フランスを中心に隆盛したレギュラシオン経済学では、労働制度に着目して資本主義をアメリカ型のフォーディズム、日本型トヨティズム、北欧型のコーポラティズムの3つに大別した。日本経済の躍進によって日本型のシステムは「ものまね」としてではなく、現代の主要な資本主義型のひとつとして着目されるに至っている。
●資本主義の混迷と「信頼」社会観—2
新しいセオリーがフランシス・フクヤマ氏の「信頼という社会ソフト」を軸に社会をみる見方だ。『「信」無くば立たず[ix]』において、フクヤマ氏は次のような概念で各国を分類する(図④)。
図④ 高信頼社会−低信頼社会
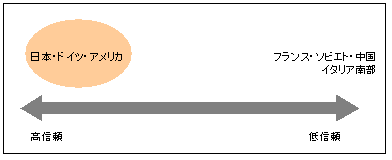
高信頼国家の代表として、日本、ドイツ、アメリカを、低信頼国家の代表としてソビエトや東欧、それに中国やフランス、イタリア(の南部)を置く。フクヤマ氏が着目するのは大企業が各国で占める地位だ。高信頼社会では、自発的な社交能力によって家族を超えて信頼感が広がり、大企業の形式が容易になる。一方、国家が長年強い統制を行い中間組織の自発的な運営能力を破壊してしまった社会では、信頼感を醸成する制度が消滅し、家族企業以上の規模で豊かな産業組織をつくり出すことが難しくなる。国家経営が比較的うまくいっている国(シンガポール・フランス・韓国)では官僚組織が中間組織を育成する機能を果たす場合もあるが、多くの場合、国家統制は社会ソフトを摩滅する方向に働く。宗教学者[x]を父に持ち「驚くべき博識」であるフクヤマ氏は、マックス・ウェーバーの宗教的社会観を基軸に、10カ国以上の現代国家に対する詳細な観察と歴史的推移の考察を織り交ぜ、まさに「グローバル社会学」とでも表現されるべき立体的な論議を展開している。
このセオリーが修正を迫られるとしたら、それはおそらくポスト資本主義社会への移行が進み、企業という単位に代わって再び「家族」が力強い産業構造を形成する単位になるなどの大変化が起こった場合—具体的にはコンピュータや家具、精密機械、ファッション、繊維など大きな設備投資を必要としないが敏速な変化対応やイノベーティブな発想が求められるソフト産業分野が急速に拡大し、おそらくはイタリア北部や台湾、中国沿海部などで、家族企業の地域ネットワーク構造が驚くべき活況を呈する—ではないだろうか。
●ケント・カルダー氏の「戦略的資本主義観」
より狭義の経済制度の研究から、フクヤマ氏と近い日本社会観をハーバード大学教授のケント・カルダー氏は主張している。カルダー氏は産業資本配分のミクロ分析を通じ、日本の経済制度研究に画期的な業績を残している。カルダー氏は、「官と民の協調」というステレオタイプの日本像に代えて、「多様な民間部門の自発的戦略性」という概念を提起した[xi]。カルダー氏によれば、産業発展のパターンは次のように示される(図⑤)。
図⑤ 産業発展のパターン
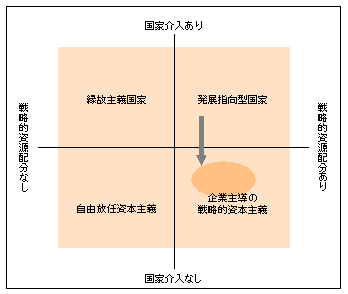
国家の戦略的な資本配分がなされているかどうか、また、それが国家の介入によってなされているかどうかの二軸で国家を分類すると、
(1)発展主義国家—国家の介入による戦略的資本配分をなす国家(韓国、シンガポール、台湾、〔フランス〕)
(2)縁故主義国家—国家が介入する戦略的な資源配分がされない国家(北朝鮮、インド、エジプト、アフリカや南アメリカの大半の国家)
(3)企業主導の「戦略的資本主義」−国家の介入は強くないが、企業による自発的・連略的な資源配分がなされる国家(日本、ドイツ、アメリカ)
(4)自由放任資本主義—国家の介入がなく、戦略的な資源配分もなされない国家(近未来のアメリカや資本主義化が加速した東欧やロシア)
となる。
日本を発展志向国家とみなすリビジョナリストの見方は、ともすれば外形的・マクロ的な国家の戦略性の有無と、国家の介入をイコールにみるものであった。一方、カルダー氏はミクロな意思決定を細かく観察し、「日本の官僚統制によらず分断されており、戦略的に動き得たのは、むしろ優れた民間部門の多様な意思決定主体によってである」と結論づけた。つまり、戦略性が必ずしも国家の介入や官僚統制によらず、自発的に生じえることを示した。これは多くの日本人の実感に合う解釈であるが、中間組織の自立性に着目する意味で、また国家の過度の関与が企業を中心とする高度資本主義社会の形成にマイナスの影響を与えるという視点に立脚しているという点で、フクヤマ氏の視点に相通ずる社会観である。
Ⅲ.混迷の時代を迎える21世紀の資本主義
さて、これからの社会ソフトの研究はどう進んでいくのだろうか。筆者は経済的なパフォーマンスや、軍事的な「チーム分け」など、闘争や競争を中心に置く世界観から社会ソフトを分類する試み—競争史観は、そろそろ一段落するのではないか、と考える。
むしろ、貧困を遥かに脱して繁栄を楽しむ、ひとり当たりのGNPで年間10,000ドルを超えるような地域—新しい中世圏[xii]—では、世界の先進国が直面している問題に対してどのような「回答」があるのかを、問題の異なりと共通点を吟味しながら、ともに探していくということになっていくのではないだろうか。
グローバルスタンダード化は、「国家や地域社会に属する人々」に対して、ダイレクトで、あるいはネットワークを介して世界と向き合う「個人」という概念を正面に押し出した。皮肉なことに、そうした「世界に属する個人」として現代の社会を眺めてみると、その悩みや辛さには共通する点が多い。生産活動がグローバル化し、多様な人種を含み、非属地化をすればするほど、個人にとっては生活領域での社会とのかかわり—暮らしやすさや生きやすさ—が大きな問題になってくるように思われる。
「新しい中世」に属する国々に共通する悩みとは—たとえば、崩壊する家庭やアダルトチルドレン、変質的な殺人者たちによる幼児殺害の恐怖、鬱病や神経症への恐怖、少子化と性風俗の紊乱、ユナボマー事件やオウムなどの熱狂的な狂信者によって行われる集団的な犯罪などである。
「近代化にもっとも成功するためには、完全に近代的であってはいけない」というのが資本主義形成期のパラドックスであった。前近代において家族や領土をまとめていた価値観が、企業組織をまとめる文化的な資産となったからである。
一方資本主義の完熟期には、「もっとも成功した近代主義国家は、前近代の社会資源を完全に使い果たしてしまう」というアイロニーが登場することになる。より早く成功した国、より大きな成功を収めた国ほど、社会のアノミー(無規範)化に悩むという意味では、日本もアメリカもドイツも、21世紀に登場するアジアの資本主義諸国も、おそらくは似ている立場にある。
私たち成功した資本主義国はどのような社会的資産を使って成功し、それをどのように費消してしまったのか。そうした資産は国によってどう違い、その費消はどのような影響を社会にあたえつつあるのか—この問題について考えるために、次のような分析を試みた。
まずは、アメリカ型、つまりアングロサクソン文明の影響下で成功を収めた資本主義について考えることにする。
『アメリカの個人主義』[xiii]を著したロバート・ベラーはアメリカ人の個人主義を4つに分類している(表①)。
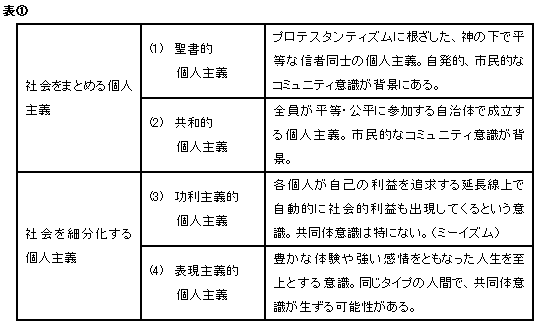
私たち日本人には一枚岩にみえるアメリカ人の個人主義も、歴史過程を経た混合物である。フランシス・フクヤマ氏がアメリカ社会の原点とみなしたのは、このなかの(1)および(2)である。アメリカでは、プロテスタンティズム的な個人主義で同時に併せ持つ強烈な共同体意識が、新しい移民層にまで共同体意識を植えつける源泉になってきた。
ところがいま、アメリカの労働組合の加入率は、32.5%から15.8%に、PTAの会員は1,500万人から700万人に、ライオンズクラブなどの友愛組織でも、この20年間で半分近く会員を減らしているところがある。つまり、自発的な共同体への帰属意識が減少し、個人が「孤人」としてありやすくなったのが現在のアメリカ社会である。
プロテスタンティズム的な個人主義—禁欲や神の下での平等性、強烈な共同体意識—こそがもともと資本主義を成立させたエートスであるが、ウェーバーや経済学者のシュンペーターの指摘によれば、資本主義の持つ功利性や創造的破壊性が、こうした禁欲精神や、共同体意識をいつしか破壊し、資本主義を内部から侵食していく。
模式的に表現すれば、(1)聖書的個人主義や(2)共和的個人主義の遺産を食いつぶしながら、(3)功利主義的個人主義や、(4)表現主義的個人主義がそれらにゆっくりと置き換わっていく、その崩壊過程が現在のアメリカ社会といえるだろう。そして、アメリカ社会に再三澎湃として起こるキリスト教原理主義(ファンダメンタリズム)の流行は、アトム化するアメリカ社会に集団的な規律やモラルを何とか社会に残そうという運動とも考えられる。
新保守主義や、ミーイズムなどの現代的な価値観は、(3)功利主義的個人主義とまさしく重なっている。一方、私たちがマルチメディアという言葉に個人の感性表現や自由な情報発信を託そうとする気持ち—かつてアップル社が提示し今日インターネット上の個人ホームページが象徴する価値観—は、(4)表現主義的個人主義に相当している。
キリスト教や共和主義の伝統のない日本やアジア諸国も(3)と(4)の個人主義は容易に会得することができる。この2つのコードは若者世代に共通する「ワールドスタンダードな個人主義的価値観」である。
Ⅳ.大きく変質した社会ソフト「日本」
現在の日本社会全体に空虚感、喪失感が漂い、かつての自律性が失われたかのように感じられるのは、なぜだろうか。それはおそらく、景気が回復すれば元に戻る性質のものではないと考える。戦国・江戸時代を経て培われ、日本社会に集団性をもたらしてきた倫理規範が根本的に失われつつあるからではないだろうか。
以下では、日本社会をまとめ日本型資本主義を成功させてきた価値観について考えてみたい[xiv](表②)。
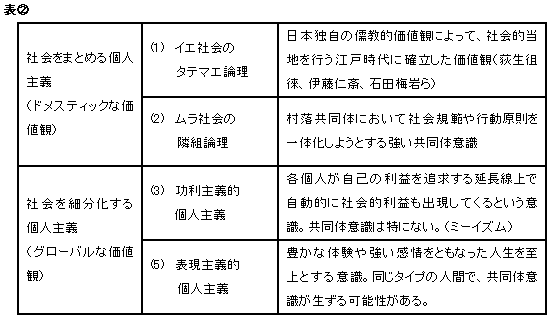
日本社会がキリスト教文化の伝統をもつ西欧の社会と大きく異なるのは、社会をまとめるのは「集団主義」であって「個人主義」でない点である。もっと分かりやすくいえば、日本の場合、社会の規範やモラルは「お上から与えられたり」「人目を気にして」生まれるもので、個人の内面には規範をつくり出す契機がほとんど存在しない。
図⑥ 価値観の相剋の異なり
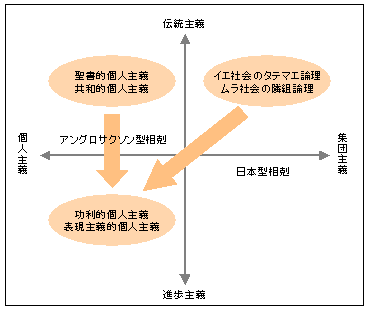
江戸・明治から現在に至るまで日本社会は、人間関係を網の目のように張り巡らせ、そこにタテマエや隣組論理を植えつけることによって、全体をひとつのユニットとしてまとめあげてきた。戦後にとりわけ目立ったのは、日本全般にヒエラルキー的なイエ社会を成立させてきた日本型儒教的倫理観を、「人目」によって維持される狭い範囲の濃密な親近信頼関係のムラ社会性を中間組織に転移してきたのである。
指導者層に西欧的な個人主義的の美徳や武士道的な倫理観がみられなくなり、本来藩というイエ社会の伝統を受け継いできた中間組織—大企業、政党、官庁—など、社会の上部組織の行動倫理は、「ウチ」と「ソト」を峻別する「ムラの論理」にすり替ってきた。つまり「一億総ムラ社会化」が進んだのである。
ところがいま、都市化やメディアの発達によって社会が細分化し、コミュニケーションは社会ではなく、個人に属し始めている。ムラ社会の隣組論理を成立させる「人目」は、企業や官庁など大部屋制の中間組織の内部を除けばほぼ消え失せた。そうした組織においてすらも携帯電話や電子メール、それに在宅勤務制度やフレックス制度は、「人目」を遮断する方向に働いている。
日本人に網の目状の規律関係を与えてきた—イエ社会のタテマエ論理やムラ社会の隣組論理はあちこちで分断化され、老朽化し、耐用年数を超えた。功利的個人主義や表現主義的個人主義などの価値観とともにあるのは、個人個人が結びついた小さなムラ社会—ムラを一歩離れればそれは異人の住む隣村—であり、いわば日本社会全体の「エスニック化」が始まっている。それが今日の日本社会の漠然たる不安感の根源にあるアノミー感覚ではないだろうか。
Ⅴ.無規範化と超集団主義の復活
—日本の「個人主義」が向かう2つの危険性
おタク文化やゲーム・マルチメディア産業、インターネットのホームページやコンピュータデザイニング…。メディア産業をカラフルに色づけているのは、強固な表現的個人主義の主張だ。あるいは新聞を飾る先端企業の裁量労働制度やストックオプション制度や実力出世主義の記事…。これらはまさしく功利主義的個人主義の果実といえるだろう。これまで過度の集団主義に囚われてきた日本社会で、多様性やユニークな創造性をもたらす個人主義の萌芽が評価され始めたのは、それなりに素晴らしいことだ。
振り返れば、日本社会の近代化が一巡しグローバル社会に直面した大正時代には、やはり現代同様、個人主義的運動が起こっている。都市化の進展を背景に、大正文化は都市文化、大衆文化としての性質を強く持った。衣食住や趣味・娯楽、思想文化の隅々に至るまで個人主義的な価値観が高まった。「柔らかな個人主義」は大正時代にすでに芽生えていたのである。
しかし、大宅壮一氏は著書『モダン層とモダン相』においてこうした動きを「(モダンの)尖端たるや、本質的生産的尖端ではなく末梢的尖端である。鋭く、細く、脆く、弱々しい尖端である」と喝破している。事実、本質的であるべき個人主義の政治・経済思想—アメリカン・デモクラシーやウィルソンが唱えた世界平和への共感や、大正プロテスタンティズムの風潮は、大恐慌の到来と軍部の台頭により雲散霧消することになった。
今日、オウム事件といった先鋭的な事件だけでなく、企業人がオカルティックな経営倫理や思想に関心を示す傾向や、個人主義のブームの陰で異常なまでのライフスタイルにおける同一主義(コギャル・ブランド品ブーム)がみられている。行き過ぎた個人主義へのバランスを取るために、ファナティックで危険な「集団主義」が生まれやすい土壌が芽生えてきたといえるのではないか。
いずれの時代、いずれの社会でも、個人主義や競争主義が社会によいパフォーマンスをもたらすのは、結束の安心感、個人主義の基盤となる良質な信頼関係が社会の成員同士にある場合である。日本の場合、その信頼感がなければ個人主義は「孤立ムラ社会」の成立を許してしまう。価値観の細分化は、消費や生活の側面では許容できても、会社や官僚、政治組織などの生産組織では「死に至る組織病」に直結する。
集団主義と個人主義を相反するものと捉えるのではなく、よい個人主義の裏づけには「よい集団主義—自立的な社会規範の共有意識」が必要だという認識が生まれなければ、日本における個人主義は大正時代同様再び皮相なものとなり、正義を体現する大きな集団主義に再び飲み込まれる可能性も高いだろう。
さて、同じく社会資源の費消が起こるにしても、アングロサクソン型資本主義と日本型(イエ社会)資本主義のあいだで、その資源のもともとの異なりが社旗のアノミー(無規範化)に対して、どのような違いを及ぼすのだろうか(図⑥)。
アングロサクソン型では、細分化を志向する個人主義の「伝統的な個人主義のすり替え」が起こっているのに対し、日本では細分化を志向する個人主義によって伝統的な集団主義の破壊が起こっている。「すり替え」は正面だった破壊ではないが、「個人主義」という美名の下で、その異なりを峻別するのはきわめて難しいだろう。
一方日本では、2つの可能性が考えられる。ひとつは、個人主義が伝統的を完膚無きまでに叩きのめす—戦国時代のような「下剋上」が社会のあちこちでおこり、戦争というかたちをとらない内乱、「家庭内乱」や「企業内乱」が起こる可能性がある。もうひとつは、こうした過激な個人主義とバランスを取る形で、規範や集団における同一性を主張する「超集団主義」が姿を変えて復活すること。かつてのように国家全体を被う集団主義の復活は難しいだろうから、たこつぼ化された集団同士の超集団主義がぶつかり合い、行きすぎた個人主義への「復習」を行う可能性もあるだろう。
いずれにせよ、日本社会が混乱に向かうのは避けられないように思える。その混乱の中から日本社会が新しい統合原理を発見し得るかどうか—そこに21世紀日本文明の帰趨がかかっているのではないだろうか。
21世紀に向けて、日本と西欧という、成功した2つの資本主義のどちらの悩みが深いのかという問いに対する回答はおそらく存在しない。しかし少なくとも、現在の日本の社会状況を、西欧の人々と分かち合ったときに生まれる、社会の成り立ちについての共通認識と、お互いの悩みへの共感が重要であることは確かであろう。
[i] フランシス・フクヤマ『歴史の終り』(上・下)、渡部昇一訳、三笠書房
[ii] Samuel P. Huntington, THE CLASH OF CIVILIZATIONS AND THE REMARKING OF WORLD ORDER, Simon & Schuster, New York
[iii] ルース・ベネディクト 『菊と刀—日本文化の型』(上・下)、長谷川松治訳、社会思想社 ベネディクトの日本観に対しては歴史上、日本社会の集団主義的な側面やエピソードだけを恣意的に取り上げているという批判がある。
[iv] ロナルド・ドーア 『21世紀は個人主義の時代か—西欧の系譜と日本』加藤幹雄訳、サイマル出版会
[v] 山本七平氏、司馬遼太郎氏の一連の著作の基本モチーフのひとつがこの時代への嫌悪感や違和感にある。
[vi] 村上泰亮・公文俊平・佐藤誠三郎 『文明としてのイエ社会』 中央公論社
[vii] ミシェル・アルベール 『資本主義対資本主義』 小池はるひ訳、竹内書店新社 ビジネスマンであったアルベール氏の直観は、レギュラシオン経済学(制度経済学)によって精緻化・学問化を深めることになった。
[viii] 大蔵省財務官である榊原英資氏の主張にもっとも色濃く表れている。
[ix] フランシス・フクヤマ 『「信」無くば立たず』 加藤寛訳、三笠書房
[x] 大阪商科大学の初代学長である河田嗣郎氏
[xi] ケント・E・カルダー『戦略的資本主義—日本型経済システムの本質』 谷口智彦訳、日本経済新聞社
[xii] 田中明彦 『新しい中世』 日本経済新聞社
[xiii] ロバート・ベラー 『心の習慣』 島薗進・中村圭志訳、みすず書房
[xiv] 佐藤俊樹 『近代・組織・資本主義—日本と西欧における近代の地平』ミネルヴァ書房、 筆者の日本社会に対する分析の多くを同書によっている。
PostCommnet
サイン・インを確認しました、.さん。コメントしてください。 (サイン・アウト)
(いままで、ここでコメントしたとがない場合はコメントを表示する前にこのウェブログのオーナーの承認が必要になる場合がございます。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらくお待ち下さい。)Warning: include_once(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /home/users/2/nzm/web/nozomu.net/journal/000004.php on line 384
Warning: include_once(http://www.nozomu.net/journal/side_category.html): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/users/2/nzm/web/nozomu.net/journal/000004.php on line 384
Warning: include_once(): Failed opening 'http://www.nozomu.net/journal/side_category.html' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/7.4/lib/php') in /home/users/2/nzm/web/nozomu.net/journal/000004.php on line 384
