マルチメディア知衆社会の到来 |
1993/12/01 メディア社会 |
これは93年に書いたものでインターネットの爆発的な発展はそれほど予感していませんでした。しかし今ブロードバンドの時代とやらが来そうになってみると、このときに書いたことを懐かしく思い出します。
目次
0.はじめに
1.映像メディアが庶民にもたらした世界化の実感
(1)庶民レベルにおける世界化の実感
(2)世界史の映像体験がもたらしたもの
(3)日本人は世界に興味を持ちつづけるか −今後の映像メディアと世界化−
2.映像メディアによる合意形成の時代 −テクスト・映像等価社会の出現−
(1) 映像メディアの登場と社会構造の変化
(2) 資本主義の2タイプの映像メディア文化
(3) 「エリート」の没落と理解の大衆化
(4) 日本独自の文字・映像併用マルチメディア社会
3.テクノロジーのフロンティアが映像産業に
(1)爆弾からテレビカメラへ
(2)メディアは技術フロンティアを担えるか
(3)メディアをめぐるパラダイムシフト −20世紀型から21世紀型へ−
(4)マッチョ・テクノロジーからハウスキーピング・テクノロジー
4.マルチメディア知衆社会のリテラシー
(1)社会・文化の視点から
“輪切り地球文明圏から櫛型地球文化圏へ”
“50%のリアリティ”
“リアルタイムでなければリアルでない”
(2)産業とテクノロジーの視点から
“「顔の見える産業社会」へ”
“ハウスキーピング・テクノロジー”
“成功のスケーラビリティ”
“メディアがブランド化する時代”
0.はじめに
情報伝達や合意形成のための社会的な道具として、また産業社会を振興する技術革新のフロンティアとして、未来の映像メディアに対する思いは強い。40年の歴史を経て、映像メディア産業は脱皮を求められている。その期待に応えることができるのであれば、これまで特殊な産業と見られてきたメディア産業が、21世紀産業社会のひとつの核として位置づけられるかもしれない。
ここでは、映像が知的な影響力を持つ社会を「マルチメディア知衆社会」と名づけた。映像を考えることは、その受け手である大衆の在り方を考えることに繋がる。「マルチメディア知衆社会」は、一部の人間に複雑な問題の解決を依存するのではなく、大勢の人間が自ら問題解決に取り組む社会でもあり、そのコンセプトは、複雑な社会現象を映像を通じて、受けて自身の問題として理解させる「理解の大衆化」、「等身大の社会」である。ここでは、「マルチメディア知衆社会」の意義を、国際化、技術フロンティア、社会的な合意形成の三点から考察し、次いで、新たな時代における、映像を媒介とするコミュニケーション(映像リテラシー)の方向性を探ってみたい。
1.映像メディアが庶民にもたらした世界化の実感 [目次へ]
「現実の複雑な世界は、テレビの単純な世界に間尺をあわせなければならない。」
−デイビッド・ハルバースタム
(1)庶民レベルにおける世界化の実感
世界規模の出来事がリアルタイムでテレビ中継され、他国で起こったことが分刻みで自分に影響を及ぼしうると日本人が初めて実感したのは、1987年のブラックマンデーの時ではなかっただろうか。地球が回り、各国の金融市場が日の出を迎えるたびに、マーケットクラッシュを起こした。その後の世界的な大事件の続発によって遠い昔のことにも感じられるが、それは、わずか数年前のことである。
他国の株式市況がリアルタイムで時刻の資本市場に影響を与えうるという、世界経済の相互関連化を金融専門家は理解していた。しかし、一般の人びとまでもがリアルに実感したという意味で、ブラックマンデーは嚆矢を放った。それは、先進国において株式所有の大衆化が進んだ後の、初めての恐怖だったのである。
その後立て続けに、東欧の革命、ロシアでのゴルバチョフに対する保守反革命のテレビ報道、湾岸戦争報道、ロス暴動と、リアルタイムの映像中継の威力を見せつける歴史的事件が相次いだ。
世界の出来事が対岸の火事ではなく、最終的に自分の懐具合と結びつくということが、庶民レベルでの世界化、相互依存化の感触ではないだろうか。世界化の実感はこれからますます、日本人の国際感覚と行動指針や意思決定のシステムを変革させるに違いない。
(2)世界史の映像体験がもたらしたもの
今世紀の初めであれば、実際に世界中の人びとの人生を大きく支配し、また数多くの名著を生み出したであろう「恐慌」「戦争」「革命」「暴動」が、1980年代の終わりに次々の発生し、世界の人びとは、こうした「大きな物語」を次々と映像メディアによって体験することになった。そして、一度こうした体験をくぐり抜けた後では、報道映像抜きでこうした現象に関心を抱き、理解することが難しくなっていることに気づく。
これまでは、第二次世界大戦の戦況や東西陣営における経済観の違いなどのように、当事者間で事実に関する正反対の見方がなされ、しかもそれが非常に長い間持続することは当然であった。イデオロギーの論理的世界に長く浸ると、異なった世界を想像することが非常に難しくなることを、近世の歴史は証明している。しかし、自由に流通する映像は、異なった世界観を持つ人の暮らしぶりや表情、服装や精神態度をそのまま映し出す。映像は、生身の自然感覚をイデオロギーが凌駕する世界の不自然さを明らかにしたのである。
世界的な規模での映像体験がもたらしたものは、世界の人びとが同じ時刻に情報に接しているというリアリティ(歴史の共有体験)を、一般大衆レベルで実感したということであろう。
その実感とは、同じ映像情報(その指し示す事実)に接すれば、民族や地域を越えて人間として同じ恐怖、興奮、刺激、快感や罪悪感を味わうという想像である。さらに、映像として外部発信が可能であれは、決して世界のなかで孤立せず、世界のどこかにその映像に触れ、感動し、共鳴する賛同者の存在が期待できるという、地球市民としての通底感でもあった。1980年代の終わりに、映像情報によってコミュニケーションするという新しいリテラシーが驚くほど急速に世界のあちこちで登場したのである。
映像メディア情報から「国境」を取り払ったのは、衛星中継の技術、テレビカメラの小型化、ビデオの大衆商品化、国際メディア企業の登場である。それぞれは小さな変革ながら、全体としては真に大きなメディア革命を成し遂げたのである。
(3)日本人は世界に興味を持ちつづけるか −今後の映像メディアと世界化−
これから先、映像メディア現象と世界化はどう関連するだろうか。1980年代終わりに起こった世界的大事件はおそらく一過性のものであり、歴史的映像のスペクタクル体験があのように大量生産される現場に、私たちはそうそう立ち会えるものではない。
しかし、世界規模の経済の緊密化と政治の相互関係化は、世界レベルでの情報の共有化への欲求をますます増加させざるをえないだろう。
ニュース的な映像が真に人を惹きつける様子はおそらく、ゴシップ、政治、スペクタクルの3つであるが、少なくともスペクタクル以外の2つの要素、ゴシップと政治の世界レベルでの映像化は今後も促進され、人びとは海外の事象に関心を持ちつづけるのではないだろうか。
大衆社会化が進む先進国において、国連やPKO、GATT、環境問題など、地球全体に対する関与は、エリートだけでなく一般庶民が、ノブレスオブリージの精神に目覚めることを前提とする。今後の対外貢献は、何がしか納税者の痛みをともなわざるをえず、ますます政治の大衆化と説得が必要になるだろう。国としてどう世界と関わるかという国際貢献の論点は、それぞれの国家でますます国内問題化せざるをえず、鋭い論争のネタであり続けるだろう。
その意味で、今後の映像メディアが人びとの世界化に果たす役割は2つあるように思われる。ひとつは、先進国と発展途上国において問題理解の共通基盤のための情報を提供することである。もうひとつは、先進国の中で、問題理解の大衆化を図ることによって、国民のなかで世界関与に対する広い合意を取りつけるという役割である。
2.映像メディアによる合意形成の時代 [目次へ]
−テクスト・映像等価社会の出現−
(1)映像メディアの登場と社会構造の変化
昭和20年代末期、テレビ時代の幕開けとともに進んだ日本社会の構造変化は、明治維新に匹敵する規模の社会変化といえるだろう。終戦後の財閥解体や農地解放などのドラスティックな変革に、マスメディアの急速な発展による社会の情報伝達構造の変化が拍車をかけた。この時期には、読売、朝日、毎日の三紙が地方社会に浸透して全国紙化を果たし、また、出版社系週刊誌が発刊されたのもほぼ同時期である。
かつては、収入や資産だけでなく、階層間の情報の隔絶によって生活様式や文化が固定化されてきた。平凡な家庭生活も、そのディーテールや価値観は他人にはわかりにくいものである。もちろん、農地改革や高度成長が主な原因であるが、加えて、生活や教養情報が階層を超えて拡散することによって、文化が隔ててきた「都市−農村、有産−無産」という階層の輪郭が急速にぼやけた。
昭和30年代から40年代にかけて、情報社会論、一億総白痴化論や中間階級論といった大衆文化論が世界に浸透したが、その多くで、映像メディアの影響が論じられていたことを指摘しておきたい。
(2)資本主義の2タイプの映像メディア文化
ミシェル・アベール氏は、資本主義には「ライン(ドイツ・フランス)型」と、「アングロサクソン型」があると指摘している。ライン型は集団意識と管理色が強い、いわば知的堅牢社会である。歴史的に広範な農村社会をひかえ、産業発展を主としてエリート階層によってきた開発型社会である。
一方のアングロサクソン型社会は、より個人主義的かつ自然発生的な市民社会である。早くから農村が縮小し、都市型、大衆社会化の進んだ19世紀中頃以降のイギリス社会がその原型である。当時のイギリス社会の特徴として、宗教の流行、ゴシップ文化、コモンセンスを逸脱しない平明さの蓄積、生きがいの喪失感などが挙げられる。こうした特長はアメリカにも一部受け継がれ、現代先進国における大衆社会化の共通基盤となっている。
明治期には、日本は典型的な農業国家であった。アングロサクソン型の発展を指向してきた筆頭参議の福沢諭吉と大隈重信が明治14年の政変で追放されて以来、伊藤博文・山形有朋両政治家によってライン型の開発型社会システムが選択され、国営の高等教育機関による教育を中心にエリート養成が図られ、官僚や軍人、実業家や法曹家が育成された。
日本では、ライン型の社会システムは、広範な農民層を擁した戦前だけでなく戦後の高度成長初期にも持続し、大きな成功を収めた。しかし、大衆社会化が浸透し、エリートを成り立たせてきた広範な農民層と農村がほぼ喪失し消費の成熟化が起こり始めた1970年代頃から、日本社会は急速にアングロサクソン型大衆社会に接近した。
わかりやすい例を挙げるなら、この頃からまじめな青少年はヘルマン・ヘッセやドフトエフスキーを読まなくなり、ポップなイギリスやアメリカ文化が知的な影響を持ち始めた。都市−農村の隔絶は、もはや日本文学のテーマたりえなくなったのである。
ところで、イギリスとアメリカは、戦後独自の映像メディア文化を形成してきたことで知られるが、イギリスにはBBCがあり、アメリカには3大ネットワークがある。文字型メディアが主としてエリート支配的な社会構造で強い影響を持つのに対し、映像メディアは、自由時間を持ち、消費者意識、政治意識の強い階層が大多数を占める社会(大衆市民社会)で影響力と文化性をもつ情報システムである。
先人たちの努力と若干の幸運もあり、日本はこの両者(BBCと3大ネットワーク)の映像メディア・システムを折衷した映像文化を形成してきた。そのことを正当に評価する人は少ないが、NHKと民法が適度に娯楽と教養を分担する産業構造が、多くの国々の映像関係者にとって垂涎の的であることは紛れもない事実である。そして、ドイツやフランスを見ても、近年の急速な自由化によって若干の活況が見られたことを除けば、戦後の消費社会においては、影響力のある映像文化は育ってこなかったように思われる。
しかし最近では、こうした国家でも急速にアングロサクソン化(大衆社会化)が進んでおり、アルベール氏の著書もこうした問題意識によって書かれている。日本は、ドイツやフランスと比べて、より早くから都市型社会構造への変化が始まり、また、アングロサクソン化現象もいち早く到来したと思われる。
(3)「エリート」の没落と理解の大衆化
今、日本では大衆文化社会の完成が最終局面を迎えようとしつつかる。1980年代以降、大学の権威が急速に崩れ、官僚に対する尊敬心も失われ始めた。高度成長期を開発型でこなしてきた社会システムが、ついに制度疲労を起こしたのである。大衆社会の進展とともにエリートの「知的権威」が低下し、100年間続いたライン型の開発社会システムの命運が尽きようとしている。また近年、データベースやメディア自身の分析機能の発展によって、大学や官庁における社会情報の収集・集積機能が評価されなくなってきているという事実が、知的権威の低下に拍車をかけている。
もうひとつ、エリート、とりわけ細分化された知的専門家に対するアンチテーゼが、色濃く主張され始めた要因がある。これは先進国に共通することであるが、高度資本主義が完成の域に近づくにつれ産業社会システムが複雑化し、一般大衆にとってはますます理解しがたいものになったのである。これまで多くの知的専門化が専門用語と瑣末な論争に終始し、簡単に、わかりやすく説明する努力を怠ってきたのは事実である。というよりもむしろ、大衆の理解は「権威」にはむしろ有害であったといえるかもしれない。
一方、メディアを通じて社会情報が拡散することによって、人びとには、より正確な社会認識を持ち、当事者意識を持って意思決定に関わりたいという渇望が芽生えた。政治の分野では、族議員化によって、政治家自身も知的専門家と化した。また、これは日本に限らず多くの先進国に共通の現象であったが、一党支配政治が続いた結果、政治家は「専門家に牛耳られ、人びとの実感を代弁してはくれない」という印象が強まった。
かくして、そこここに、高度化し専門化し理解しにくい社会システムに参画を迫られながら、問題が理解できないという強い矛盾感が生じている。高度化と専門化が、理解の「疎外」を招いてきたのである。今日、原発反対や環境問題などの反産業的な運動が一定の支持を集めるのも、こうした疎外感と強い関わりがあろう。
今、社会システムに対する「等身大の理解」への渇望が強まっている。たとえば、税配分を複雑な政治・官僚システムに任せることによってブラックボックス化するのではなく、負担と用途が比較しやすい目的税別のシステムへ移行する傾向が見受けられるようになってきた。要するに、わかりやすい税制が望まれているのである。
忙しい毎日において、複雑な事柄を「わかりやすく説明される」ことが人びとにとって重要なのであり、社会理解のツールとしての映像メディアの有効性が評価されつつある。映像メディアは、一般の人びとに代理体験とリアリティを提供する「理解の大衆化」の道具となったのである。
今日、識者の高説が社会の合意形成に大きな役割を果たすことはほとんどない。自分自身でものごとを理解し、自分自身の意見をもちたいという人びとが増えるにつれて、映像メディアによる情報が合意形成に果たす役割は増大している。
(4)日本独自の文字・映像併用マルチメディア社会
少し古い話になるが、NHKスペシャル『緊急土地改革・地価は下げられる』(1990年10月)は、人びとの実感、疑問感を限りなく明確化して土地バブル終焉のきっかけとなった印象がある。同じく『電子立国・日本の自叙伝』(1991年1月)は、社会的な記憶と語り部の役が映像表現によって狙われる時代の到来を予感された。
こうした映像メディアの地位と役割変化の背景として、メディア経験の世代交代が進みつつあることを指摘することができるだろう。生まれたときから映像メディアに接した映像メディア世代に(昭和30年代以降生まれのポスト団塊世代)が、消費・生産の両面で社会の前面に出つつある。この世代は、映像メディアに対する過度の恐怖も期待も抱いていない、映像メディアとともに歩んできた世代である。
生まれたときから映像メディアに接してきた世代の価値観の特徴は、文字と映像、あるいはロジックとイメージが等しい価値を持つ、いわば等価主義である。世代交代によって、文字尊重の文化から文字・映像併用のリテラシーへと、社会全般の理解の重心が移動しつつある。それは、社会的な合意形成をもたらす知的な影響力が、テクスト中心の分析・蓄積能力から映像を併用した構築・表現能力へと移りつつあることを意味する。
しかし、映像メディアだけがこうした影響力を持つようになることはありえないだろう。今日の日本社会を眺めると、テクストを否定するのではなく、映像とテクストが相互に補完・検証し合うメディア社会が形づくられている。例えば、毎年出版点数は増加する一方である。また日本は、漫画という文字、画像を扱う粗情報メディアが知的な影響力を持つという、世界的にも珍しい国である。さらに、今後のテレビの多チャンネル化は、知的なテレビ視聴の可能性を増大させ、その中には、活字メディアとの連携をさらに強めるものも出てくるだろう。
こうしたメディアの相互関連現象に、すでに日本型マルチメディア社会の萌芽が隠されている。
3.テクノロジーのフロンティアが映像産業に [目次へ]
(1)爆弾からテレビカメラへ
湾岸戦争では、スマート爆弾の先にテレビカメラが搭載され、爆弾そのものが中継された。そのシーンは、技術のフロンティアが武器からメディアへ移行したことを強く実感させた。爆弾の効果が爆弾自身によって報道され、その世界的な影響力は甚大であり、世界の人びとは、スマート爆弾の「スマートさ」は爆弾の誘導効果によってではなく、テレビカメラの制御機能としてよりよく機能していると受け取った。
これは、現代を代表するテクノロジーの震源地と恩恵先が、軍事分野から民生(メディア)分野へ完全に移行したいという事実を示す象徴的な出来事でもあった。
冷戦の終了後、現代産業社会のテクノロジーのフロンティアをどこに見出すかという議論が起こり、「冷戦の勝者は日本とドイツであり、敗者はアメリカとソ連である」とデイビッド・ハルバースタム氏は指摘した。
その勝敗は、一国の技術フロンティアを軍事に置いた大国と、民生消費財においた小国との、技術パラダイム競争の帰趨である。軍事組織に中心においた一極集中型の「恐竜型技術」から、数多くの民生品メーカーに主導による自立・多極分散型の「哺乳類型技術」へと、パラダイムシフトが起こったのである。
軍事に基礎を置いた技術パラダイムの特徴は、少品種、巨大、集中、高価であり、民生技術のそれは、多品種、軽薄、分散、安価である。冷戦終了後、民生産業における技術パラダイムのフロンティアが通信・メディア市場に強く求められ、こうした市場が次世代における技術パラダイムの突破口と目される状況が起こっている。
現代は、産業の付加価値がモノから情報ソフトに移行する時代である。特に先進国のあいだでは、情報通信技術の優劣が次世代の国家インフラのキーであり競争力を決めるとする見方が多数派となりつつある。アメリカのゴア副大統領が光ファイバー政策の積極論者として知られるのはあまりにも有名であるが、環境問題がクローズアップされるにつれ、エネルギー多消費型の政策ではなく、メディア系・ソフト系の省資源型産業に対する産業傾斜が好ましいという議論も起こってきている。
通信、メディア、ソフト、コンピュータ、家電などの産業が融合し、いわゆるマルチメディア産業が次世代の「産業の米」であるとする論者が多い。コンピュータや通信の能力が増大する一方でドラスティックなコストダウンが進んでいるが、膨大な演算能力を使う広大なマーケットは、今や映像処理以外に見つからない。映像メディアのマーケットが、市場のフロンティアを担う勢いを見せている。
(2)メディアは技術フロンティアを担えるか
しかし、民生産業に技術フロンティアを求める変革は、社会にとって非常にリスクの高い技術開発の方法論である。
ニューメディア・ブームにおいて、メディアに過度の期待が集まり、それが成就されなかったのは偶然ではない。ニューメディア・ブームは、消費者の要求よりも技術オリエンテッドな要求に基づいてきたといえるが、同じ失敗は、今回のマルチメディア・ブームでも起こりつつある。
かくしてメディア産業に、産業社会全般のブレイクスルー役の期待がたびたび押し付けられる一方で、新しいテクノロジー産業というものは、信頼性に欠け、コストも割高であることが多い。
消費者は技術にはまったく無頓着であり、ひたすら安くてよいものを歓迎する。前述のように、核戦争の恐怖のもとであれば核実験の失敗に何回でも耐えられるが、放送衛星の契約者は、衛星の打ち上げの失敗にそう何回も耐えられるものではない。「先物買いの銭失い」にも限度があり、先端的な技術革新のコストを先端消費者のみに担わせることは難しい。
より多く、より早く、より高性能にという、高度成長期に成功したときと同じやり方とメンタリティーで消費者に社会全体を進展させる技術革新コストを背負わせようとしても簡単にはいかない。テクノロジー開発と消費者の欲求をすり合わせる努力が、これまで以上に必要となるだろう。
(3)メディアをめぐるパラダイムシフト −20世紀型から21世紀型へ−
メディア産業を進展させるためには、新たな技術パラダイムがかなりの程度花開くまでの旧来型のテクノロジーや社会システムを用いざるをえなかったり、その圧迫や摩擦に耐えることが欲求されるが、その典型的な例が放送・通信衛星である。人工衛星は原子力と同じく、冷戦下に開発が行われた「恐竜型」の巨大技術であり、人工衛星を使った放送通信技術は、広大な領土、同一の言語圏と文化をもつアメリカ、ソ連、中国などの20世紀型の超大国においては確かに効率のよいメディア・システムである。その意味で、放送衛星は真に革新的なメディアではなく、20世紀型のシステム、つまり、旧来型の技術パラダイムに属しているといえる。
長期的に見れば、デジタル通信網が21世紀型、つまり「哺乳類型」の社会情報インフラを形成することになるのかもしれない。多くの人びとが、大脳のシナプスにも似た網目状ネットワークが先進国を覆う光景を予想している。しかし、技術の成熟やコスト、ファイナンスなどの問題で、こうした映像メディアを中心とする新たな技術体系が完成するまでに、かなりの時間がかかるだろう。したがって、しばらくの間は、旧来の技術との折衷によって斬新的な革新を目指さなければならない。その道筋は複雑で、明確な指針を持ちにくいものとなろう。
(4)マッチョ・テクノロジーからハウスキーピング・テクノロジーへ
次世代の技術パラダイムはどのようなものであろうか。20世紀型の技術は、基本的に道具の延長線上にあるビジブル(目に見える)な技術体系であり、飛行機、ロケット、巨大工場、原発、大型コンピュータなどは、ある意味でマッチョ(男性性を誇示する)な技術体系でもあった。しかし、消費者が開発コストを負担する社会では、過度のマッチョさ(技術指向)は、ひとりよがりとの批判を避けられない。これからは、インビジブルで(目に見えない)、どこか優しく便利な、ある意味で「女性的な」技術体系が主流になるだろう。
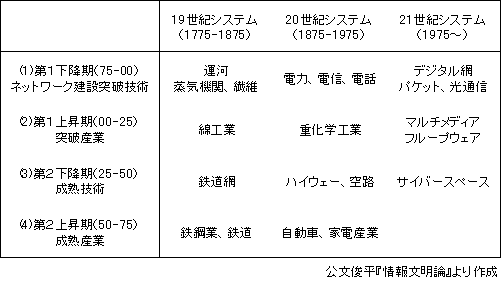
今日求められているのは、社会全体の技術体系を目に見えないネットワークによって統合する、成熟したテクノロジーである。進歩や発展から「こなれている、痒いところに手が届く」「等身大のサービス」へと、テクノロジーの開発の方向が変化しつつある。マニアやおたくでなくても、一般の人びとが誰でも使いこなせる技術、いわば「ハウスキーピング・テクノロジー」がキーワードとなろう。
今後の社会においては、テクノロジーが単独で突出することはますます歓迎されなくなる。技術を使う人と産業システム、コストパフォーマンスやリテラシー(文化)が、技術と轡を並べて進む必要がある。技術開発のコスト負担、リスク負担を大衆が背負う社会においては、技術開発の必要性の広範な理解や合意が不可欠である。人びとの理解を得ることが、技術者にとってもっと重要な仕事になるかもしれない。
現在、コンピュータとテレビの融合、スマートTV(賢いテレビ)やマルチメディアをめぐってさまざまな技術開発が行われているが、使い方を含めた新たなメリットや産業発展の道筋を提示できなければ、絵に描いた餅になる危険性もある。人びとにわかりやすい技術、等身大の技術を提供できた企業こそが勝者となるのではないだろうか。
4.マルチメディア知衆社会のリテラシー [目次へ]
世界化、技術、政治、産業などの社会システムの見方についても、映像メディア世代は新たな文脈をもたらすだろう。マルチメディア知衆社会において、映像情報を読み取るリテラシーはどのように変わるだろうか。ここでは、社会・文化と産業・技術の視点から、来るべき変化のコンセプトを何点かランダムに指摘しておきたい。
(1)社会・文化の視点から
“輪切り地球文明圏から櫛型地球文化圏へ”
20世紀の世界は、主として南北方向に分節されてきた。先進国が主に北側にあり、中緯度に中程度の国家が位置し、発展途上国が団結する南半球では別世界という、産業化の度合いを軸にした輪切り(同緯度)方向が地球を構造化してきた。つまり、旧ソ連とアメリカは東西で対抗してはいたが、超大国という文脈では同じ世界に位置していたのである。
しかし、世界中でリアルタイムで映像情報に接する機会が増えると、同じ時間に同じ時刻を迎える経度方向の人びとの連帯感・共同生活感がこれまで以上に強まるのではないだろうか。ビジネスの領域でも、テレビ電話システムなど通信メディアの革新が進み、リアルタイム性がより強く求められてくるだろう。リアルタイム・メディアの増加は、1日を同じリズムで(朝は朝、夜は夜)歩む人びとの共同性を高めるだろう。映像メディアの世界化により、南北問題の解決は同じ経度同士でという垂直指向が、より強まるかもしれない。日本はアジアを、アメリカは南アメリカを、ヨーロッパはアフリカをという「櫛型地球文化圏化」の始まりである。
“50%のリアリティ”
近い将来、映像のデジタル制作が日常化すると、映像の改変が容易になるばかりか、改変された証拠が何も残らないという問題が露呈してくるだろう。
例えば、すべてが名プレーだけで構成されているようなバスケットボールのドリームマッチを創作することも可能になる。また、歴史上の人物との対談や架空のゴシップの創作なども可能である。こうした作業はすでに、コマーシャルや映画で実際に試みられているが、デジタル化されていれば改変の証拠は何も残らない。文字情報と異なり、改変が容易に読み取れたり、改変の証拠が残ったり、あるいは改変に非常にコストがかかるという現実によって保たれてきた映像の証拠価値は、遠からず半減するかもしれない。そのことは、私たちがこれまで抱いてきたリアリティの概念を大きく変えることになるだろう。
事実か事実でないかの白黒をはっきりさせるのではなく、30%のリアリティ、70%のリアリティといった概念が登場してくるに違いない。また、ドキュメンタリー番組のやらせ問題についても、異なった基準で判断されることになるのではないだろうか。さらに、映像を誰が撮影し編集したのかということが、映像の意義を知る上でより重要になってくる。テロップやバックグラウンドで、常に報道者・制作者に関する情報が流れているというようなことが日常化するかもしれない。
“リアルタイムでなければリアルでない”
リアルタイムで映像の改変を行うことは非常に難しいために、リアルタイムの映像情報のリアル性はこれまで以上に重要になり、視聴者はリアルタイムであればあるほど映像にリアリティを見出すという新たなリテラシーが登場してくるだろう。また、一度消費された映像はニュース価値を急速に失わざるをえず、自ずと各メディア企業はリアルタイムへの競争を行うことになる。
最近では、地震のニュースなどで素人が撮影したビデオ映像が用いられることが多くなりつつある。ロス暴動のシーンも、ヘリコプターに搭載された小型のテレビカメラによって全米に中継された。現在でも、画質にかかわらず、より早く、よりリアルな情報に対する要求が高まってきているが、将来はこうした傾向がますます加速されていくに違いない。
“「文は人を表す」から「話し方は人を表す」へ”
またマルチメディア社会においては、人物に対する評価基準、特に知的水準の目安が、会話の簡潔性や論理性、ユーモア度やわかりやすさ、適度の感情表現能力、さらに、表情や服装を含めた全体的な表現能力に依存するようになる。そうした傾向は国際化による多文化コミュニケーション増大の当然の帰結でもある。
(2)産業とテクノロジーの視点から
“「顔の見える産業社会」へ”
アメリカ社会における芸能、スポーツ、クリエイターや知的タレントの長者番付を見ると、100億円以上の申告所得が目白押しである。税制の違いを考慮する必要はあるが、こうした所得の多さは「セクシーでダイナミック」なアングロサクソン型大衆社会の特徴である。
今後の日本社会では、より一層の大衆社会化・映像社会化が進展し、メディアが増加することによって、ソフトの売り手市場化が進む。その結果、音楽家、建築家、キャスター、作家、脚本家などのソフトクリエイター側に、イニシアチブと付加価値が移行することが予想される。現在も進行中である特定個人の人物イメージを核にしたソフト制作のシステム化は、ますます加速していくだろう。ハードの製造と異なりソフトの制作には、個性の強いクリエイターを協働させるだけの、強力な個人によるイメージ統率力と共同体性が不可欠になる。特定の個人を中核にソフト生産を行う、いわばヒューマン・インダストリーの拡大化が進展し、産業規模としても無視できないものとなっていくだろう。
“ハウスキーピング・テクノロジー”
家電製品の個人化はほぼ飽和状態になりつつあり、これからは、モノではなくサービスの個人化がポイントになるだろう。例えば、見たい番組を検索してくれたり、自動録画したり、必要な情報を記憶するといった、賢いテレビが求められるようになる。こうしたサービスは、目には見えないバックグラウンドでさまざまな処理を行う、ハウスキーピング的なテクノロジーによって実現されていくだろう。そうした環境を実現するためには、ソフトとハードが切り離されて商品化されるのではなく、ソフトとハードを含めた技術体系のシステム化が必要であり、システム化に際してはデジタル化も重要なポイントになる。
“成功のスケーラビリティ”
任天堂のファミコンやインターネットが成功を収めたのは、普及に合わせたソフトとハードの投資規模の調節が可能であったためである。ハイビジョンや放送衛星が苦戦を強いられる原因は、成功するためのハードルが非常に高く設定され、実際にビジネスを展開してみるまでマーケットが存在するかどうかわからないという点にあり、いわば目隠しをして棒高跳びをするようなリスクをともなう。それは、経済学的に言えば、固定コスト、サンクコストが大きい産業形態であることを意味するが、今後は、投資の規模に合わせた成功、成功のサイズにあわせた投資が可能な「成功のスケーラビリティ」という概念が重要になってくるだろう。
“メディアがブランド化する時代”
多メディアになればなるほど、逆に視聴者は、特定のメディアを指向・選択するようになる。番組単体の優劣だけではなく、楽しさ、信頼性、報道の迅速さ、年代別の相性など、メディアのイメージによってチャンネル選択が起こるようになり、さらに、メディア企業間のこうしたブランド・セグメントに拍車をかけるだろう。
メディア企業やグループのコーポレート・アイデンティティの強さがより多くの視聴者からの支持を集めるようになるが、その結果、メディアのブランド化がますます進むことが予想される。
PostCommnet
サイン・インを確認しました、.さん。コメントしてください。 (サイン・アウト)
(いままで、ここでコメントしたとがない場合はコメントを表示する前にこのウェブログのオーナーの承認が必要になる場合がございます。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらくお待ち下さい。)Warning: include_once(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /home/users/2/nzm/web/nozomu.net/journal/000002.php on line 501
Warning: include_once(http://www.nozomu.net/journal/side_category.html): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/users/2/nzm/web/nozomu.net/journal/000002.php on line 501
Warning: include_once(): Failed opening 'http://www.nozomu.net/journal/side_category.html' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/7.4/lib/php') in /home/users/2/nzm/web/nozomu.net/journal/000002.php on line 501
